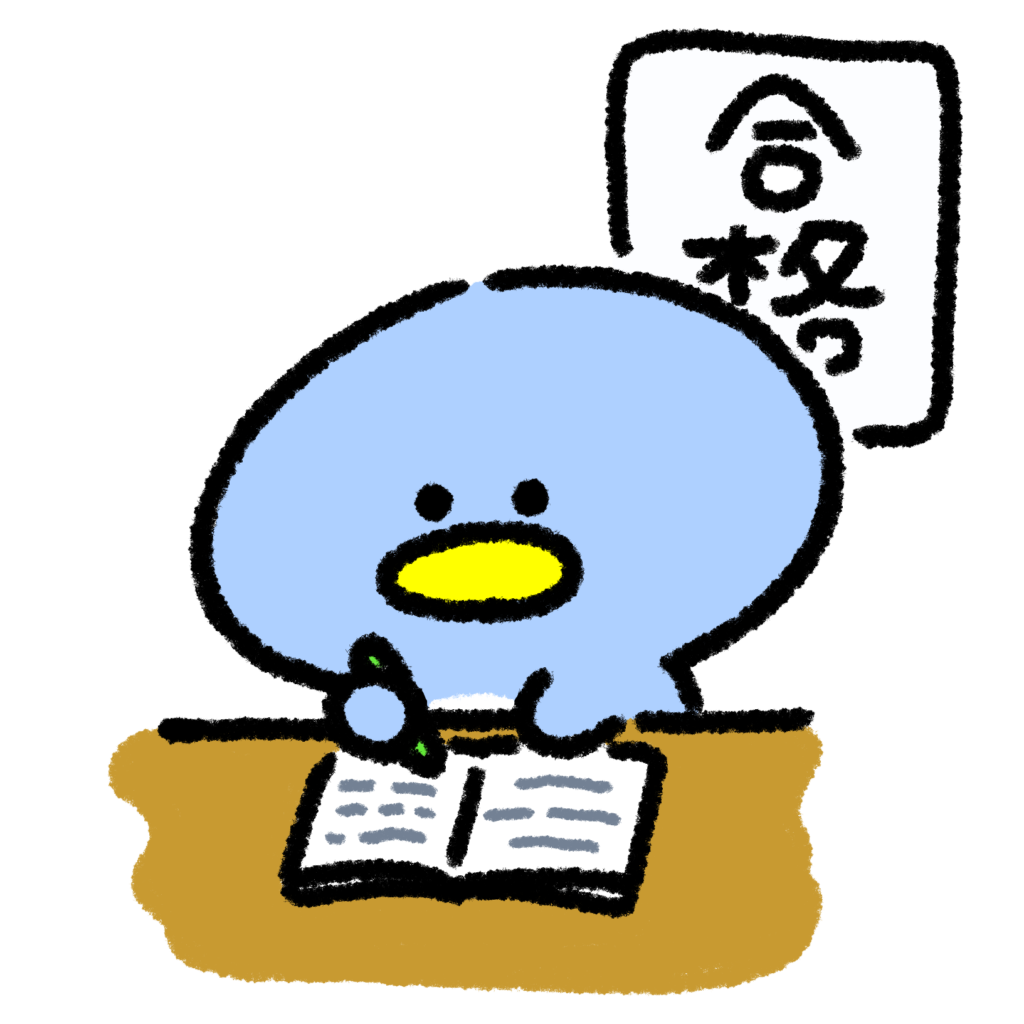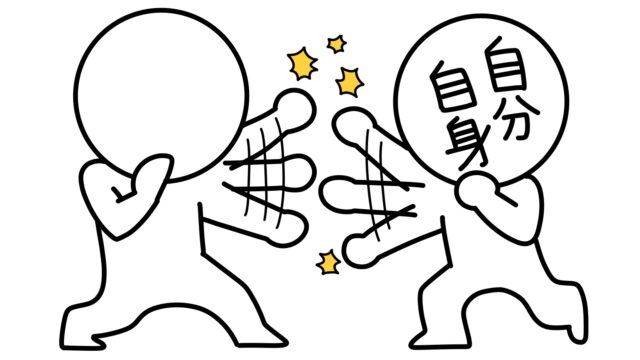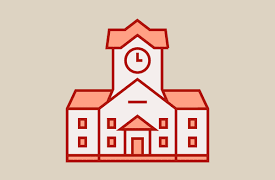こんにちは、のこのこです🐢
4月になり、いよいよ受験生としての1年が始まった!と気合いを入れている方も多いと思います。
今は「やってやるぞ!」というモチベーションでいっぱいでも、数ヶ月後には
「……あれ?あのやる気、どこいった?」なんてこと、よくあるんですよね。
今回はそんな受験生活の中で、多くの人がつまずきがちな“10の罠”とその対処法について、
私の実体験も交えながらお話ししていきます!
というのも、私自身は大学受験で2浪を経験しています。
「もっと早く気づいておけば…」と今でも思うことがたくさんあって、
それを今、受験に向き合っているあなたに伝えられたらと思っています。
この記事が、受験生ご本人はもちろん、その親御さんにとっても、
「そうそう!これ大事!」と感じてもらえるようなヒントになれば嬉しいです。
それでは早速いきましょう!
1. 完璧主義になりすぎる
受験勉強でありがちなのが「1問でも間違えたら先に進めない」「100点取れなきゃ意味がない」といった完璧主義です。
結論、これは非効率です。
理由はシンプルで、受験は“100点を取るゲーム”ではなく、“合格点を超えるゲーム”だから。例:合格点が80点の試験だったら?
100点を目指して全範囲を完璧にするよりも、
「落としてもOKな20点」を見極めて、
確実に取るべき80点を逃さない勉強をする方が圧倒的に効率がいいです。実際、本番で満点を取る必要はありません。
むしろ「この問題は後回しでOK」と判断できる人の方が強いです。✅ 完璧主義を捨てるメリット
限られた時間を有効活用できる
得意分野を伸ばして得点源にできる
本番で冷静に戦略を立てられる
✅ 解決策:合格点主義に切り替えよう
「全部できるようにする」よりも「合格に必要なことだけに集中する」方が成果が出ます。
例えば、得意分野を後回しにして、苦手分野を伸ばすだけでも点数は大きく変わります。「全部わからなくても受かる」
このマインド、大切です。
完璧を求めすぎると、時間もやる気も削られます。
最終的に勝つのは、うまく力を抜いて戦略的に動ける人です。✅ まとめ:戦略的に“サボれる”人が受かる
完璧主義=努力家っぽく見えて、実は落とし穴。
合格したいなら、やるべきことだけに集中しましょう。
完璧じゃなくていい。必要なのは、受かるための点を取ることです。
2. インプットばかりでアウトプット不足
「参考書めっちゃ読んだのに模試の点数が伸びない…」
そんなとき、原因の9割はアウトプット不足だったりします。
✅ インプットだけじゃ力はつかない話
勉強って、「読んだら終わり」じゃなくて、
**「使って初めて身につく」**んです。
スポーツなら、ルールだけ覚えて試合に出ようとしてるようなもの。
ピアノなら、楽譜だけ読んで本番に出る感じ。
…いや、それ無理ゲーでしょ?って話です。
✅ 本当に力がつくのはアウトプット
過去問を解く
問題集で手を動かす
間違えたところを分析して反省する
この“解いて・ミスって・直す”ループこそが、点数につながる最強の流れ。
知識は、アウトプットしてこそ「使える武器」になります。
✅ アウトプット勉強の具体例
教科書を1時間読むより、問題集を30分解く
単語は「書いて・声に出して・使って」覚える
解けなかった問題は「なんで間違えた?」を振り返って、反省ノートを作る
この流れで「理解 → 演習 → 定着」のサイクルが回り始めます。
✅ まとめ:点数を伸ばしたいならアウトプット
インプットだけじゃ点は取れません。
読むだけ、聞くだけでは“できるようにならない”んです。
勉強はアウトプットが8割。
「わかる」と「できる」は別物。
点数を伸ばしたいなら、今日から“手を動かす”ことを意識していきましょう。
3. SNS・スマホ依存
「気づいたらYouTube見てた…」
「5分だけのつもりが1時間経過」
これ、受験生あるあるですよね。
✅ スマホって“ドーパミン製造機”です
SNSの通知、動画のサムネ、スクロール無限ループ…。
全部、“あなたの脳に気持ちよくなってもらうため”に設計されてます。
つまり、ハマって当然。
意思の力でコントロールしようとするのは、ちょっと無理ゲーなんです。
✅ 「ちょっとだけ」から抜け出せないワケ
LINE返信したら、ついInstagramを開いちゃう
勉強の合間にTikTok → 気づけば1時間経過
通知音ひとつで集中が一気に崩壊
これ全部、スマホの仕様上そうなるようにできてるんですよね。
✅ 解決法は「環境で断ち切る」
スマホ依存は、根性論じゃ勝てません。
だからこそ、物理的に“距離を置く工夫”が大事。
💡 スマホ依存から抜け出すための3つの工夫
スマホを別の部屋に置く
視界に入るだけで集中が削られます。別室推奨。アプリに時間制限をかける
「SNSは1日15分まで」など設定。おすすめアプリ:「Focus To-Do」「Study Bunny」など。週1のデジタルデトックスDayをつくる
スマホ断ちをするだけで、頭がスッキリする感覚になります。
✅ 通知音は集中力クラッシャー
せっかく集中できてきたタイミングで「ピコッ」って鳴ると、
脳の“注意力”は一気にリセットされてしまいます。
なので、通知は全部オフ+サイレントモードに。
✅ まとめ:スマホはコントロールして使おう
スマホは使い方次第で「味方」にも「最大の敵」にもなります。
受験勉強において一番大事なのは、“集中力を守る環境づくり”。
今日からは、スマホに支配されるんじゃなく、
**「自分が主導権を握る」**意識でいきましょう。
4. いろいろな参考書に手を出す
「これも良さそう!」「あの人が使ってたやつ、気になる!」
でもちょっと待って。
それ、本当に全部やりきれる?
✅ 買っただけで「勉強した気」になってない?
新品の参考書を手に取って、
パラパラ…「おお、なんか勉強できる人っぽい!」って気分になる。
わかります、自分もそうでした。
だけど、それだけじゃ成績は1ミリも伸びません。
✅ 成績が上がる人は、1冊を“使い倒してる”
合格者の多くが言います。
「この参考書、ボロボロになるまで使った」
なぜなら、知識って繰り返して初めて“自分のもの”になるから。
あれもこれも手を出すと、全部が中途半端に。
結果、問題を見ても「見たことあるけど…解けない」状態に。
✅ 参考書の「数」より「回転数」が大事
本当に身につくのは、
同じ問題を見た瞬間に解法がスッと浮かぶ状態。
それを目指すなら、新しい参考書を買うんじゃなくて、
今手元にある1冊を何周も繰り返す方が断然効果的です。
✅ 参考書との“正しい付き合い方”
最初の1冊は王道でOK
学校指定や定番の参考書から始めよう。「わからない=他の本へ」じゃない
別の本に逃げる前に、解説を読み込んで、自分で考えるクセを。3周以上して初めて“使った”と言える
1周では不十分。最低3周はやり込んで、記憶に焼き付けよう。
✅ まとめ:参考書は“数”じゃなく“使い込み”が命
本棚にズラッと並んだ参考書より、
ボロボロになった1冊の方が、圧倒的に信頼できる武器になります。
あれこれ浮気せず、まずは1冊と本気で向き合うこと。
それが、合格への最短ルートです。
5. 睡眠不足・生活リズムの乱れ
「夜のほうが集中できるし!」
「昼間は眠いから、勉強は深夜が捗る!」
その言葉、ちょっと待った!
✅ 睡眠舐めてると、後悔するのは自分
受験生あるあるで、夜に詰め込んで頑張ってる人、多いけど、
実はそれ、集中力・記憶力・判断力をまとめて落とす最強の“デバフ”になるんです。
そして怖いのが、自分では「大丈夫、まだいける!」と思ってても、
脳はヘロヘロ。
眠さに支配されたままだと、思考の精度がどんどん落ちて、結局勉強効果が低くなっちゃうんですよ。
✅ 昼夜逆転でメンタルがやられる
夜型の生活が続くと、
ただリズムが崩れるだけじゃなくて、
無駄に自己嫌悪したり、やる気が出なくなったり、
情緒不安定になったりしがち。
「また昼過ぎに起きちゃった…やばい…」って感じで、
そのまま負のスパイラルにハマっていくことが多いんです。
✅ 生活リズムが整えば、勉強効率もアップ
生活リズムこそ、勉強力の土台。
毎日同じ時間に寝て起きる
できるだけ23時〜7時の間に寝るとベスト。朝型生活が、入試本番にも役立つよ!寝る1時間前にスマホ・PC OFF
ブルーライトが脳を覚醒させて、寝つきが悪くなります。
眠れるルーティーンを作ると◎(読書やストレッチとか)夜型がどうしても直らないときは朝型を少し試す
最初は大変だけど、1週間ちゃんと朝型にするだけで、
日中の集中力が驚くほどアップしますよ!
※もちろん、夜型の方が体質にあっているという人は無理して変える必要はありません。
✅ 睡眠=脳の“最強の暗記タイム”
実は、寝ている間に脳が記憶を整理してるって知ってましたか?
しっかり寝ないと、覚えたことが定着しにくいんです。
そのため、勉強時間を削ってでも寝るという判断は、
実はかなり賢い選択だったりするんですよ。
✅ まとめ:まずは“脳のコンディション”を整えることが肝心
夜更かしして勉強しても、結局ぼーっとしてるなら意味ない。
睡眠時間=脳のメンテナンスタイム。
「寝るのも勉強のうち」って気持ちで、
まずは生活リズムを整えることから始めてみましょう!
それが、最終的に成績に直結しますよ!
6. 模試の結果に一喜一憂しすぎる
模試の結果が返ってくる日って、
やたら緊張するし、ちょっとソワソワしますよね。
「A判定きたー!俺もう受かるやん!」
「E判定…終わった…もう無理…」
ちょっと待った、それは罠です。
✅ 模試は「ゴール」じゃなくて「現在地」
模試って、あくまで今の立ち位置を知るものです。
通知表じゃないし、合否を決めるものでもありません。
一番大事なのは、模試の後にどう動いたか。
✅ A判定の“油断” VS E判定の“覚醒”
よくある話ですが、
A判定をとって安心して手を抜いた人より、
E判定から「マジ悔しい、見返したる…!」ってスイッチ入れた人の方が、
最終的に受かるってケース、めちゃくちゃ多いです。
模試の結果を“ゴール”みたいに感じると、
思考停止して勉強が止まる。それが一番危険。
✅ 大事なのは“分析と改善”
模試の使い方で差がつきます。
間違えた原因をチェックする
ケアレスミス?時間足りなかった?知識不足?原因をしっかり分解。出題傾向と自分の弱点を照らす
いつも同じ系統で落としてない?クセを知れば対策できる。「じゃあ次どうするか?」を決める
模試は“成長のヒントが詰まったイベント”です。
数字に一喜一憂するより、「改善点」を見つけにいく姿勢が大事。
✅ 成績は“スナップ写真”でしかない
模試の判定はあくまで“今この瞬間”の状態。
成績は、上がったり下がったりして当然です。
でも、それが全体として右肩上がりなら問題なし。
模試で落ち込んでるヒマがあったら、
1つでもミスを分析して次に繋げた方がコスパ最強です。
✅ まとめ:「模試後、どう動いたか?」がすべて
模試の判定が良かったからって安心しすぎるのはNG。
逆に悪かったからって落ち込んで止まるのもNG。
受験はまだ終わってません。
むしろここから何度でも巻き返せる。
模試は「点数」じゃなく「ヒント」を見つけるもの。
結果をバネに、次の一手を考えていきましょう!
7. 勉強している“つもり”になる
「今日、8時間も勉強したのに全然進んでない…」
そんな日、ありませんか?
それ、実はただの「勉強した気になってるだけ」かもしれません。
✅ 「机に向かってる時間=勉強」じゃない
ノートを広げて、ペンを握って、単語帳をめくる…。
一見、勉強っぽく見えるけど、
スマホ触ってた
ボーッとしてた
他のこと考えてた
こういう時間、実はめっちゃ多くないですか?
脳が動いてないなら、それは勉強じゃないんです。
✅ “勉強時間”と“集中時間”は別物!
1時間ダラダラやるより、
30分ガチ集中してやる方がはるかに効果的です。
受験勉強は、「長時間やった感」じゃなく、
どれだけ密度の濃い時間を過ごしたかが勝負。
解決法①|ポモドーロ法で集中を強制!
おすすめなのが「ポモドーロ・テクニック」。
25分集中 → 5分休憩(これで1セット)
4セットごとに長めの休憩
このリズムでやると、「とりあえず25分だけ頑張ろ」って気軽に始められて、
ダラダラ防止になります。
📱 タイマーアプリ(例:「Focus To-Do」)を使えば、より管理しやすい!
解決法②|成果を“見える化”する
勉強の成果は、数字で記録するのがコツ。
英単語100語中80語覚えた!
数学の演習10問中8問正解した!
参考書◯ページ進んだ!
…こうやって進捗を見える化すると、達成感が出てモチベも爆上がりします。
✅ ノートの端にメモ
✅ 勉強日記アプリに記録
✅ Googleスプレッドシートで管理
自分が“何をどれだけやったか”がハッキリすると、やった気だけで終わらなくなります。
✅ まとめ:「時間」より「集中」。
勉強は“時間の長さ”じゃなく、“中身の濃さ”で勝負。
「机にいた時間=勉強した」は錯覚。
タイマーと記録で、つもり勉強から抜け出そう!
「やった感」じゃなく「やった実感」が残る1日を積み重ねていこう!
8. 周囲と比べて焦る・落ち込む
「◯◯くん、A判定だって…」
「え、あの子もう青チャ2周目らしい…」
そんな話を聞いて、なんか自分だけ置いていかれてる気がしたこと、ありませんか?
でも、それって全部 “他人の話”です。
✅ 他人の進捗 ≠ 自分の評価
受験って、つい他人と比べがちだけど、
ゴールも違う
得意不得意も違う
今までの積み重ねも違う
つまり、土俵がそもそも違うんです。
そこを無視して落ち込んでも、何もプラスにならない。
SNSは“メンタルブレイカー”
「今日の勉強時間12時間✌️」
「Z会、全範囲制覇!」
…こういうの見て、焦ったことあると思います。
でもそれ、たいてい“映えフィルター”なんです。
成果が出た日だけ投稿
うまくいった部分だけ切り取ってる
失敗やスランプは投稿されない
現実はもっと地味で、泥臭くて、日々の積み重ね。
見える世界だけを真に受けないこと!
焦るとペースが崩れる
「やばい!自分もペース上げなきゃ!」って焦ると、
勉強法を変えちゃう
無理に詰め込みすぎる
本来のプランがめちゃくちゃになる
結果、集中できずに成果も出ず、自己嫌悪ループへ…。
解決法①|“視線”を他人から自分に戻す
他人の進捗 → 見ない
自分の目標 → 書いて毎日見返す
「今日、昨日より1歩前に進めたか?」
これだけに集中してOK。
比べる相手は“昨日の自分”だけでいい。
解決法②|SNS断ち or 距離を置く
SNSって、受験期に限って言えばノイズです。
アプリ消すのが無理でも通知オフ
ログイン回数を制限
勉強垢は“見る専”じゃなく“発信専用”にするのも◎
LINEなど連絡ツールだけ残して、
それ以外はしばらくフェードアウトするのもアリ!
✅ まとめ:焦る暇があったら、自分の今日を整えよう
他人と比べて病むより、昨日より1問多く解ける方が価値ある
SNSや他人の進捗はスルーでOK
勝負するのは「昨日の自分」だけ
焦らず、惑わされず、
あなたのペースで、着実に一歩ずつ。
9. 計画倒れの勉強スケジュール
「英単語100個!数学2時間!現代文30分!…よし完璧🔥」
→ 3日後:「全然進まない…やばい…もう無理…」
このループ、心当たりありませんか?
それ、理想詰めすぎ型の“計画倒れ”パターンです。
✅ 計画って“立てて満足”しがち
完璧な計画を立てた瞬間って、めちゃくちゃやる気出ますよね。
でも、
想定外の用事が入った
寝坊した
思ったより疲れてた
…そんな日も普通にあるんです。
つまり、最初からズレる前提で作らないと崩れる。
ガチガチスケジュールは、むしろ非効率
「8:00 英語長文」「9:00 古文単語」みたいな分刻みスケジュール、やったことある人多いと思うけど、
これ、ズレたときのストレスやばくないですか?笑
ちょっとトイレ行っただけでズレて
→ 焦る
→ パニック
→ 結局、崩壊
むしろ、「午前は英語ざっくり」「午後は数学中心」みたいなゆるブロック型のほうが断然続きます。
解決法①|“ざっくり&毎週見直し”がちょうどいい
毎日やることは3つまでに絞る
週末に「できた・できなかった」を軽く振り返る
来週の計画にリカバリ時間を組み込む
スケジュールは“完璧に守る”より、
**“微調整しながら前に進む”**のが大事。
解決法②|“余白”を意識して入れる
予定をギッチギチに詰めると、1つズレただけで全部崩壊します。
だからこそ、
「水曜は予備日」
「毎日1時間は“自由勉強タイム”」
…みたいに、余白時間をあえて作るのがコツ。
この余白があるだけで、リズムも気持ちも安定します◎
✅ まとめ:“気合”じゃなく“仕組み”で回す
気合で無理な計画を立てて→崩れて→落ち込んで…
を繰り返すと、自己肯定感がゴリゴリ削れます。
小さな成功を積み上げて
続けられるプランを作って
「回ってる自分」に自信を持つ
受験は長期戦。勝つのは、無理なく回せる仕組みを持ってる人です!
10. 「まだ時間あるから」と先延ばし癖
「夏から本気出す」
「今週は忙しいから、来週から」
「まだ11月だし、焦るの早くない?」
――このセリフ、超よく聞く。
でもそのままズルズルいって、気づいたら時間切れってパターン、めっちゃ多いです。
✅ 一番ヤバいのは「何もしない日」が続くこと
受験勉強って、一夜漬けじゃ無理。
コツコツ積み上げるしかない戦いなんです。
でも、「今日はまあいいか」って日が3日、5日、1週間と続くと…
取り返すには時間が足りないレベルに。
そこから一気に焦って
→ やる気なくす
→ 自信なくす
→ 勉強からさらに遠ざかる
っていう、負のスパイラルに入っちゃいます。
「やる気が出たらやる」は、だいたいやらない
やる気ってね、天気と一緒。
昨日晴れてたのに今日はどんより、なんて当たり前。
つまり、やる気を待ってたら一生始まらない。
解決法①|まず“5分”だけやってみる
やる気がないときは、とりあえず
英単語1つ見る
数学1問だけ解く
みたいな、小さすぎる第一歩を踏み出してみて。
不思議なことに、5分やると脳が起動して「もうちょっとやろうかな」ってなる。
ポイントは、**“始めるまでが一番重い”**ってこと!
解決法②|タスクを“細切れ”にする
「世界史30ページ読む」って考えると、めっちゃしんどい。
でも「1ページ読む」なら、今できそうじゃない?
ゴールがでかい →「今日はやめとこ」
ゴールが小さい →「ちょっとだけやっとくか」
この心理的ハードルの差が、先延ばしを防ぐカギ!
✅ まとめ:「いつかやる」は、たぶん一生やらない
未来の自分に任せると、結局なにも進まない。
「今日できる1個の小さなこと」
これを、毎日ちょっとずつ積み上げていこう。
やる気は、「やったあと」に生まれるもの。
だから、まずは動こう。それだけで、未来は変わる!
おわりに
ここまで読んでくれて、ありがとうございます!
受験って、どうしても
「もっと頑張らなきゃ」
「サボっちゃダメだ」
って気持ちに追われがちです。
でも、今回紹介した“受験の罠”は、ほとんどの受験生が一度はハマることばかりです。
だからこそ、「自分だけじゃない」って、ちょっとホッとしてもらえたら嬉しい。
🎯 大事なのは、“完璧”じゃなくて“前進”
1日1問でも、できたなら前進。
今日はやる気が出なかった…でも、少しだけやってみよう。
受験において一番大事なのは、柔軟に軌道修正しながら続けること。
むしろそれができる人が、最終的に一番伸びる。
自分のペースで、自分らしく。
焦らなくて大丈夫。
SNSの誰かと比べなくていい。
今の自分を認めて、小さな一歩を重ねていこう。
最後まで読んでくれたあなたの、
受験がうまくいくように、心から応援しています!
—— のこのこ 🐢